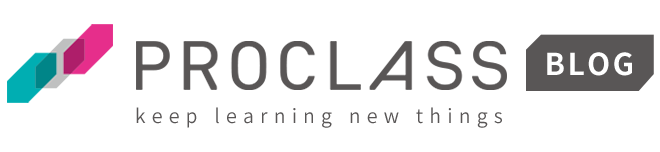こんにちは、プロクラスの和方です!
私は普段プログラミング教室の講師として仕事をしています。
多くの生徒と関わる中で毎回いろんな気付きがあるのですが、今回は「学校の勉強とプログラミング学習の違い」について書いてみたいと思います。
以前、プロクラスでは授業の節目にテストを実施していたことがありました。
(※現在は創作課題を単元ごとのまとめとして行っているためテストは行っていません)
その時、ある生徒がテスト対策として必死にコードを丸暗記していたことがありました。
一度解いた問題がテストとして出題されるケースもあったので、暗記するのも意図としては納得できます。
しかし、いざテストになると、長いコードを覚えきれずに不合格に…。
ここで私は「勉強=覚えること」という習慣に強く違和感を感じました。
実は、日本の学校教育では「覚えること」がまだまだ根強い部分があります。
その影響からか、プログラミングも「記憶の延長」として捉え、丸暗記しようとする子が一定数います。
もちろん学力テストの要は「覚えたことをいかに早く答えるか?」ですし、いろんな知識を覚えること自体が無意味だと言いたいわけでは一切ありません。
知識は社会に出てからも役立つ重要な土台です。
ただ、社会を生きる上で「記憶」だけが活躍するかというとそうではなく、「答えのない課題に向かう力」や「コミュニケーション力」など、いろいろな力を組み合わせることが必要になります。
私たちの役割は、そんな「勉強=覚えること」という先入観を少しずつ解きほぐし、「答えがない時にどうするのか?」や「ダメだった時にどうするのか?」という経験を増やしてあげることだと考えています。
私はプログラミングの講師なので、具体的な取り組みとしては、
●同じ問題でも少しずつ条件を変えて(答えを一つに絞らずに)チャレンジしてもらう
●バグやエラーが出た時などにすぐに答えを教えるのではなく、原因を探すサポートをする
など行っています。
そして、こうしたアプローチが、子どもたちの理解を深め、自ら考え抜く力を育てる鍵になると感じています。
もし、今回の記事をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひ一度プロクラスの無料体験にご参加ください!