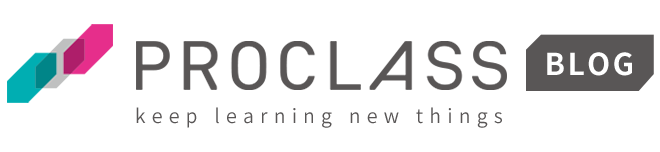こんにちは、プロクラスの和方です!
私は普段プログラミング教室の講師として仕事をしていますが、指導を行う中で様々な取り組みを行っています。
今回は「自分で作ったプログラムについて説明することの大切さ」について書いてみたいと思います。
プログラミング学習の初期段階では、「なんとなく動かしても問題が解けてしまう」ことがよくあります。
特に順次処理や1重の繰り返しといった基礎レベルでは、エラーが出ても少しコードをいじるだけで直ってしまうため、表面的な理解のままでも進めてしまうのです。
しかし、学習が中盤に差しかかり、条件分岐や変数、複雑な繰り返しが登場してくると、これまでの“なんとなく”では通用しなくなります。
その段階で初めて、「なぜそう書くのか」を理解していなかったことに気づき、挫折してしまう生徒も少なくありません。
こうした問題を防ぐために、学習の初期段階から取り入れたい指導法の一つが「プログラムを生徒自身に説明させる」というアプローチです。
たとえば完成したプログラムを生徒と一緒に見ながら次のような問いを投げかけます。
「このプログラムはどんな順番で処理が行われているの?」
「この部分ではどんなことが行われているの?」
「もしこの処理がなくなったとしたら、どんな不具合が起こると思う?」
こうした問いを通して、生徒は自分の書いたプログラムを“言葉で説明”する必要が出てきます。
ただ「できたからOK!」ではなく、「なぜそう書いたのか」「この部分は何をしているのか」といった“意味”を自分で整理することになり、自然とプログラムを客観的に見る力が育ちます。
講師の方はというと、生徒の説明を聞くことで、どこまで理解できているか、どの部分が曖昧なのかを具体的に把握することができます。
このように対話を通じて学習を進めることで、単なる「動くプログラムを作る力」だけでなく、「考え方を言語化し、理解を深める力」も養うことができるのです。
結果として、理解の地盤がより強固になり、後半の学習でつまずきにくくなります。
さて、いかがだったでしょうか?
大人でも自分の考え方を客観的に捉えたり、人に伝えたりすることは必要になります。
子供の頃から説明する機会を持つことは、将来の子供達にとっても役にたつ力になると思います。
もし、今回の記事をご覧になって興味を持たれた方は、ぜひ一度プロクラスの無料体験にご参加ください!